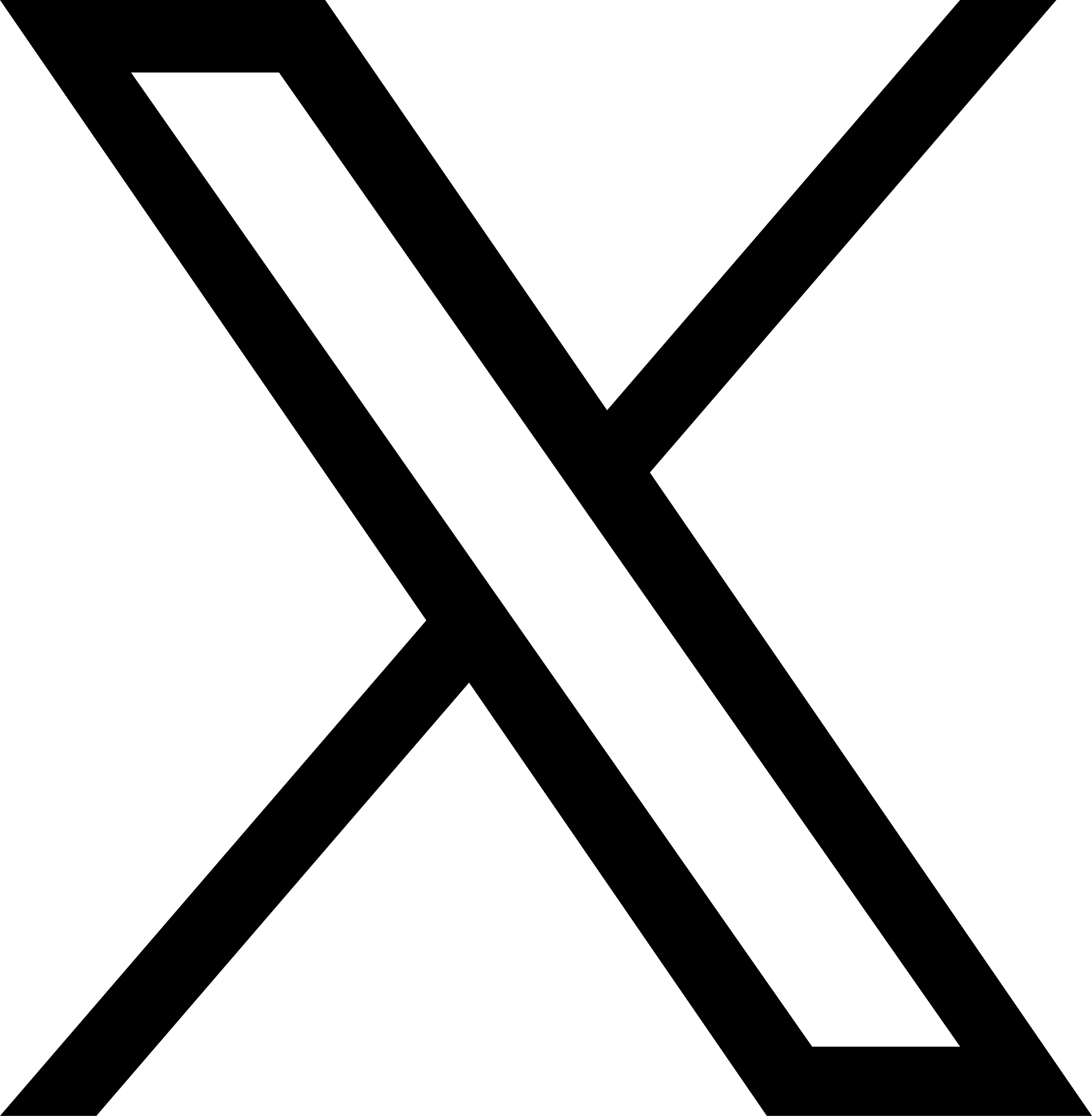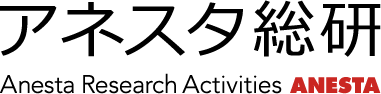高校生の大学選びは、偏差値よりも「自分らしさ」が活かせる環境に注目し、その大学が持つ「教育力」で選ぶ時代へと変わりつつあります。
「教育力」を示すキーワードとして注目されるのは、経団連が社員採用において重視する資質として挙げるコミュニケーション能力、主体性、協調性、チャレンジ精神を育む力です。
一方で、企業にとって人材の確保は、競争の激しい業界で生き残るために必須です。さらに、優秀な人材を採用することは、企業が発展を続けるために欠かせません。
今回は、新規採用の現場で豊富な経験を持つ株式会社クロスキャット 管理統括部人事部長・細根宇紘氏に、大学卒業生の採用に求められる力と、大学教育への期待についてお話を伺いました。
●Profile
細根 宇紘(ほそね・たかひろ)
株式会社クロスキャット 管理統括部 人事部長。
2004年入社後、エンジニアとしてクレジットカードのシステム開発などに従事し、300名規模のプロジェクトを率いた経験を持つ。2016年より人事部に異動し、採用戦略や働きやすい職場づくりに取り組んでいる。
――事業内容について、わかりやすくご紹介ください。
私たちクロスキャットは、主に企業や官公庁といった法人のお客様に向けて、システムを作り、運用しています。
たとえば官公庁では納税に関わるシステムを開発しました。金融の分野では、みなさんがネットショッピングやお店でクレジットカードを使ったときに、決済が正しく処理されるように、裏側で支えるシステムを作っています。
こうしたシステムは普段あまり目に触れませんが、人々の生活を支える社会の基盤そのものです。
1973年に創業し、現在は東証プライム市場に上場しています。特定の大企業やメーカーの系列に属さず、自分たちの力でシステム開発を行う「独立系SIer」です。事業展開の自由度が高く、多様な分野に挑戦できるのが特徴です。
――大学の新卒生の採用や学生に求める力について、近年の状況を教えてください。かつては「入社してから育てる」というのが一般的でしたが、最近はいかがでしょうか。
従来は、入社後に企業が育成することが前提でした。
しかし近年は、大学で最先端の技術を学んできた学生が、入社直後から即戦力として活躍するケースが増えています。
特に生成AIやクラウド、数理最適化といった分野では、大学での学びがそのまま当社の強みに直結します。
ですので当社でも「高度スペシャリスト採用」という制度を設け、通常の新卒の2倍の年収で採用する枠を用意するなど、学生時代の専門性を重視する動きが強まっています。
――採用において、経団連が重視する資質として「コミュニケーション能力」がよく挙げられます。
ただ、この言葉は幅が広く、具体的にイメージしにくい面もあります。どのように捉えていらっしゃいますか。
コミュニケーション能力は非常に広い概念で、人や状況によって意味が変わります。
私の考えでは、①自分の考えをしっかり伝える「発信力」、②相手の話に耳を傾ける「傾聴力」、③相手の気持ちに寄り添う「共感力」に分けられると思います。
これらは要するに、人と人との関係を円滑に進める力です。企業で働く以上、誰にとっても欠かせない力であり、採用においても「なくてはならない力」と位置づけています。
――面接の場で、学生がどの程度のコミュニケーション力を備えているのかを判断するのは難しいように思えます。どのような方法で見極めているのでしょうか。
当社の社員の多くはITエンジニアで、チームを組んでプロジェクトを進めています。そこで重要になるのが、自分の考えを正しく伝える「伝達力」と、相手の意図を理解する「把握力」です。これを確かめるために、採用面接では「プレゼンテーション試験」を行っています。学生には自分の強みや将来やりたいことをテーマに発表してもらい、その後の質疑応答を通じて、把握力や伝達力を確認しています。
――企業で働き続け、成長していくためには、主体性やチャレンジ精神といった力が大切だと言われます。
それらを伸ばすための土台となる資質はどのようなものだとお考えですか。
最も大切だと思うのは「自責思考」です。「自分に原因がある」と考えられる人は、自然と主体的に動き、チャレンジする力を伸ばしていきます。反対に「他責思考」、つまり周囲や環境のせいにばかりしてしまう人は、成長のチャンスを逃しがちです。
例えば当社はIT系の企業で、各種のベンダー資格や国家資格の取得を推奨しています。合格者には報奨金も支給しますが、実際に挑戦するかどうか、次の試験までにどう準備するかは本人次第です。自責思考を持つ人は「資格を取得することは自分の成長になり良いキャリアにつながる」と捉え、学習計画を立てて挑みます。こうしたサイクルが確かな専門性を生み、結果的にプロジェクトやチームを支える力に結びつきます。だからこそ、自責思考は成長の原動力であり、社会に出た後も長く大切にしてほしい資質です。
――最近は高校や大学で「アクティブラーニング」が取り入れられるようになっています。実際に採用の場から見て、こうした取り組みはどのような効果があるとお考えでしょうか。
アクティブラーニングこそ、主体性を養う場だと考えています。実感として、大学でアクティブラーニングを積んできた学生は、主体性が高く、発信力があり、必要に応じてリーダーシップも発揮できる人が多いです。
また、人の成長発達の特性から言っても、入社後に初めてこれらを身につけるのでは遅いという意見があります。
中学生から大学生の時期に、アクティブラーニングを通じて成功体験・失敗体験を重ね、自己肯定感を育むことが重要です。自己肯定感が乏しいと、「自責思考」が形成されにくく、入社後に実力があっても力を発揮し切れない場面が生まれます。例えば『私にはできません』『そんなことないよ。新人の中ではできる方だよ』という、もったいないすれ違いが起こりがちです。
失敗を次のプロセスに前向きに活かせないのは、経験の不足と自己肯定感の弱さが背景にあることも多い。採用企業としては選考でストレス耐性も見ていますから、きれいに見えるキャリアや学習履歴以上に、どんな失敗を経験し、そこから何を得たのか――その内実を重視しています。
――ご自身のこれまでの歩みについても伺いたいと思います。学生時代から現在の人事部長に至るまで、どのようなキャリアを歩んでこられたのでしょうか。
中学・高校では卓球部に所属し、厳しい部活動中心の生活でした。大学では社会学部で学び、当初は新聞記者を志していましたが、就職氷河期で募集が極端に少なく進路に悩みました。
数学が得意だったこともあり、ITエンジニアの道を選び、2004年にクロスキャットへ入社。クレジットカード関連のシステム開発などに携わってきました。
2016年から人事部へ。現場での経験を活かしながら、採用戦略や働きやすい職場づくりに取り組んでいます。
――今回の取材は、神奈川工科大学のご紹介により行われました。同大学では1・2年次のプロジェクト教育を中心とするアクティブラーニングで得た経験を、3・4年次の研究室教育で活かすように設計されています。その点も踏まえて、同大学の教育を採用の観点からどのように評価されていますか。
神奈川工科大学の学生は、専門分野の学びがしっかりしていて、研究室での少人数教育を通じて主体性や発信力を磨いていると感じます。人間的にもバランスが良く、ここ数年は新卒採用60名のうち毎年6〜7名が同大学の卒業生です。当社にとっても重要な採用先になっています。
――これから進路や将来を考える高校生、保護者に向けて、メッセージをお願いします。
これからの就職で大切なのは、学歴や偏差値だけではありません。
大学で専門性をしっかり磨き、仲間と切磋琢磨し、失敗から学ぶ経験を重ねることが重要です。そうした主体性やチャレンジ精神を持つ学生は、企業にとって非常に魅力的です。ぜひ、自ら学び、挑戦し続ける姿勢を大切にしてください。