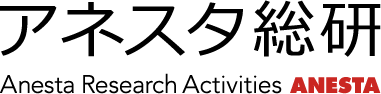さまざまなモノがインターネットにつながり、私たちの生活を支えてくれる技術「IoT (Internet of Things)」。「モノのインターネット」と訳されるこの技術は、近年急速に実用化が進んでいます。身近な例ではスマートウォッチやスマートスピーカー、自動運転車などがありますが、他にもさまざまな分野で実用化に向けた研究が行われています。東洋大学情報連携学部(略称:INIAD)の別所正博先生は、この技術をコロナ禍における社会課題の解決や、障がいがある方の“困りごと”の解決などに応用。三密回避につながる産学連携プロジェクトを実現させた他、研究室の学生たちとともにさまざまなアプリの開発にも取り組んでいます。
街の混雑状況を知らせる「No! 三密プロジェクト」

私は「デジタル技術を応用した社会課題の解決」をテーマに、主にIoT (=Internet of Things)について研究を進めています。IoTとは、身の回りのもの、例えば家電や家具などの“モノ”にコンピューターを入れてインターネットとつなぎ、情報をやりとりする技術を指します。
現在は主に3つの研究に取り組んでいます。ひとつ目は「コロナ禍におけるIoTの活用」です。コロナ禍によって新たに出てきた課題を解決しようと、三密を回避する行動や、本学部におけるオンライン教育を支援する技術の研究を行っています。
三密回避支援については、テレビ局のTOKYO MXや凸版印刷といった民間企業と連携して「No! 三密プロジェクト」を実施しました。まず、「COCOA」というアプリが発するBluetoothの信号を利用して、街中の混雑状況をリアルタイムで観測する技術を新たに開発しました。そして、COCOAの電波を検出する端末を繁華街や商店街などに置き、その周りにどれだけ人がいるかを計測できるようにしたのです。

この技術をもとに混雑を予報するシステムも開発し、2021年2月からは各地の混雑度を誰でも見られるようWebサイトで公開しています。TOKYO MXの番組内では混雑予報のコーナーにデータ提供も行いました。また、このアイデアを応用して、研究室の学生と一緒にソーシャルディスタンスを促すデジタルサイネージ(平面ディスプレイなどに映像や文字を表示するシステム)も開発しました。
「盛り上がりDetector」でスポーツ観戦をより楽しく

2つ目の研究テーマは「IoTを用いた障がい者支援」です。これは、スマートフォンやスマートウォッチ、スマートグラスなどを活用して、障がいのある方を日常の困りごとに寄り添う形で支援しようというものです。スポーツ観戦中の聴覚障がいのある方に周囲の観客の盛り上がり度をスマートウォッチで知らせる「盛り上がりDetector」の他、視覚障がいのある方の自販機利用をスマートフォンで支援する仕組みなど、さまざまなアプリを開発して実証実験を続けています。
3つ目は、「オープンデータに関する研究」です。ここでは、行政や企業などが持つデータ、例えば交通情報などを公開してもらい、すべての人がインターネットを通じて利用できるようになる社会の実現をめざしています。現在、情報の公開や流通について研究するとともに、学部長の坂村健先生と一緒に「公共交通オープンデータ協議会」という産官学連携の協議会も運営しています。
今後も、IoTをはじめとするデジタル技術を使って、社会のさまざまな困りごとを解決していきたいですね。私は、デジタル技術にはそれだけの力があると信じています。今、デジタル技術の分野ではどんどん新しいものが誕生していて、コンピューターなどを学ぶ人にとっては非常に面白い時代にあります。学生の皆さんにも、ぜひ本学の情報連携学部でコンピューターを学んで、それを社会に出た後に直面するさまざまな課題の解決に活かしてもらいたいと思います。
COLUMN
INIAD(東洋大学情報連携学部)のキャンパスは、最先端のIoT技術によって、照明や空調などさまざまな設備機器がネットワークに接続された「IoTキャンパス」。別所研究室の学生は、IoT研究に最適な環境のなかで、社会課題の発見や解決策の実現に取り組んです。
『I→technology(アイテクノロジー)』03号より転載。
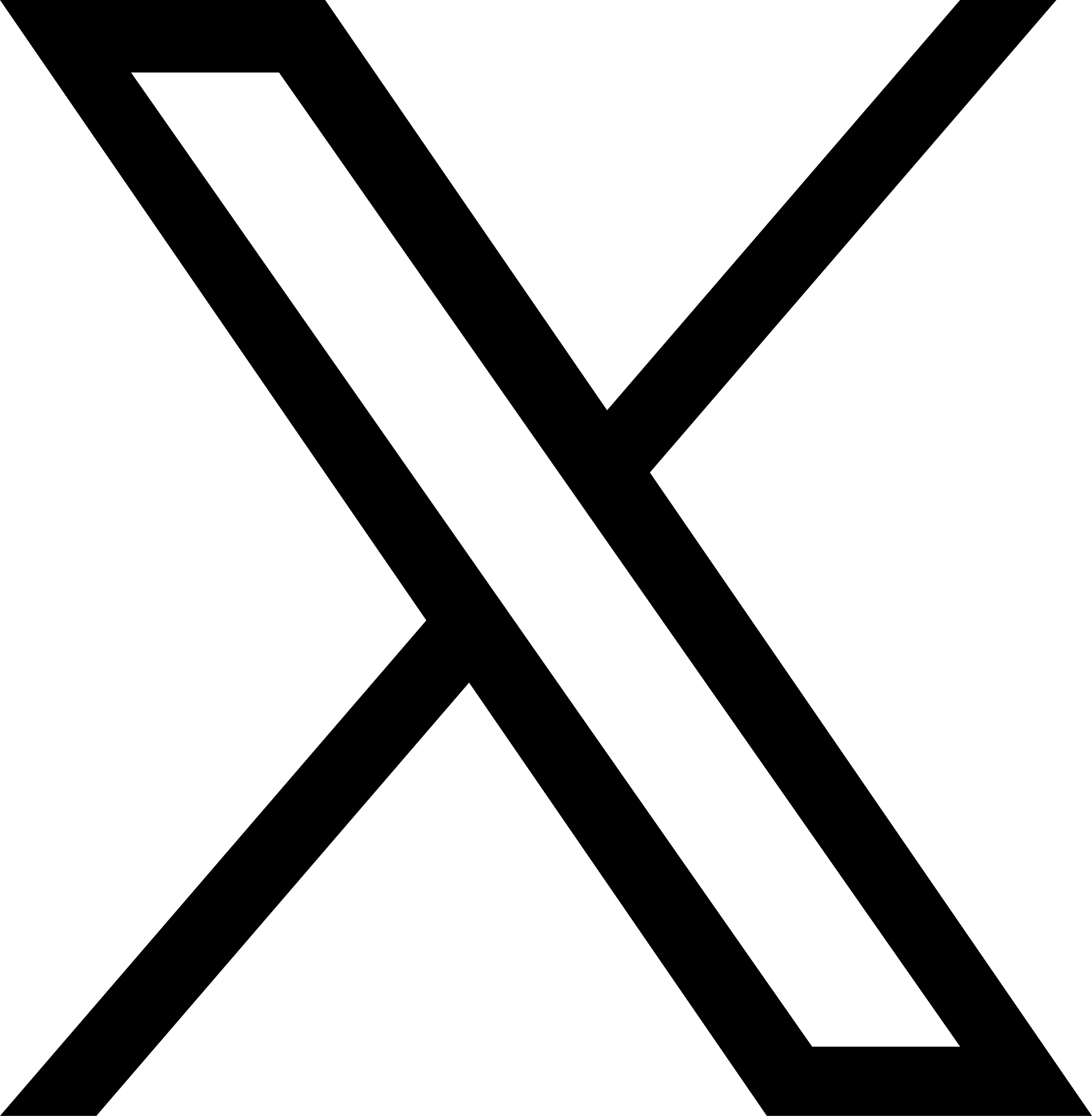








.jpg)